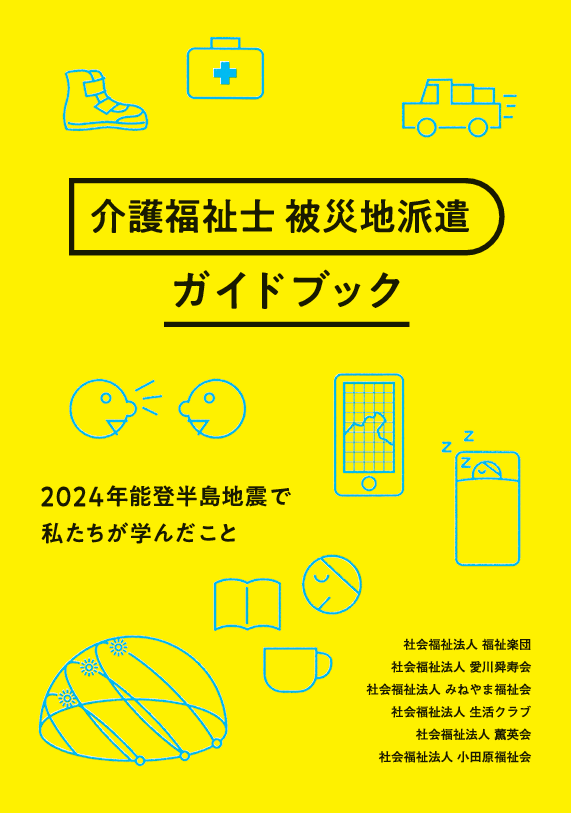事例研究発表会とは
潤生園では日々のケア実践を事例研究というかたちで蓄積しています。
各事業所の研究結果を発表する場が毎年開催される事例研究発表会。
毎年3日間に渡り開催され、約15~16事業所が日々のケア実践について発表を行います。そして例年100名以上の職員や関係者が発表を聴きに参加します。
2018年度からはナイチンゲール看護研究上の金井一薫先生にご指導を頂きながら、「KOMケア理論」をテーマに取り上げて発表が行われてきました。
KOMケア理論とは
https://nightingale-a.jp/komi-care-theory/
回を重ねるごとにケアの実践も研究としての質も高まっています